- 官と民をまたがる越境キャリア支援ならVOLVE
- 公共セクターへの転職
- VOLVE記事一覧
- 経産省で“民間経験者”は活躍できますか?【経産省・小林秘書課長×VOLVE吉井】
経産省で“民間経験者”は活躍できますか?【経産省・小林秘書課長×VOLVE吉井】 2025.04.30

経済産業省はいま、民間企業で経験を積んだ人材などを対象にした「経験者採用」に力を入れています。
一方で民間企業から経産省に転職する場合、大きな環境の変化もともなうため、不安に思うことも多いと思います。
民間と霞が関では昇進に違いはあるのか、経験者採用で入省して責任のある仕事ができるのか……。
経産省秘書課長・小林大和さんに、VOLVEの吉井がインタビューしました。
・小林 大和(こばやし・ひろかず)
経済産業省大臣官房秘書課長 ※2025年4月時点
1973年生まれ、神奈川県出身。1996年東京大学法学部卒業。2001-02年にケンブリッジ大学及びロンドンビジネススクールで修士号を取得。
1996年通商産業省入省。以来、通商政策、エネルギー政策、環境政策、自動車政策などを担当。2023年から現職にて省内の人事・組織開発全般を担当。経済産業研究所(RIETI)コンサルティングフェロー兼務。
・吉井 弘和(よしい・ひろかず)
VOLVE株式会社代表取締役、慶應義塾大学総合政策学部准教授
1981年、東京都生まれ。2004年東京大学理学部数学科卒業。11年米国コロンビア大学及び英国ロンドン大学政治経済学院より公共経営学修士(MPA)を取得。
2004年マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社、同ドイツ支社転勤、英国保守党本部インターン、同社アソシエイト・パートナー、社会保険診療報酬支払基金理事長特任補佐、厚生労働省保険局保険課課長補佐を経て現職。
年次主義ではなく「能力実績」を重視

吉井 まず初めに、国家公務員の人事制度について伺います。
2025年3月に有識者会議「人事行政諮問会議」がまとめた提言では、人材確保に向けて給与水準の引き上げを求めています。具体的には比較対象とする民間企業を「50人以上」から「100人以上」に、キャリア官僚については「1000人以上」と比較することを提言しています。この提言についてどのように感じましたか。
小林 全体として、改革の方向性がポジティブに示され、霞が関で働く私たちにとって元気が出る内容です。中でも、ご指摘の給与水準は、今回の報告書のコアの部分だと思います。
激しい人材獲得競争の中で、霞が関がどのような企業と競っているのかが明確に意識されています。最も大切なことは仕事のやりがいですが、職責と処遇が見合っているかどうかは、人材獲得においてやはり大事なポイントでしょう。
吉井 提言書の中には「年次に縛られず実力本位で活躍」という言葉もありましたが、民間から霞が関への転職では「年次主義」もハードルになると感じます。
小林 経産省の人事の基本的な考え方は、能力実績主義です。能力が備わっているか、実際に能力が発揮されたか、つまり成果を生んだかどうかの両面で見ています。
他の省庁と比べても、経産省は能力実績主義が強く意識され、実際に運用されています。多くの職員もそう感じていると思います。
能力と実績と言ったときには、もちろん経験も重要になります。経験の蓄積によって能力が高まり、大きな実績が出てくる面があります。ただし、それが行き過ぎて硬直的な年次主義につながってしまうことは、避けなければなりません。
民間企業はこの20年間、年次主義から大きく脱却してきました。40代の役員も珍しくありませんし、同じ入社タイミングでも昇進スピードが大きく異なることは普通のことです。
霞が関でも、これまで以上に経験者採用が増えてくれば、「何年に入省した」ということなどはどんどん相対化します。能力や実績に基づいて人材が評価され、見合ったポジションに就いて行くことが、ますます当たり前になるでしょう。そのことを通じて、霞が関が本来持っている力が一層発揮されていくはずです。
30代で民間の「部長級」への昇進も
吉井 能力実績主義というのは民間企業にも近い考え方だと感じます。ただ、実際に若くても昇進できるのでしょうか?
小林 お答えする前に、少しだけ構造を解説しておきます。霞が関で「課長補佐」と呼ばれるポジションは、概ね民間企業のマネージャー、課長職に相当すると言って良いでしょう。5人から10人くらいのチームを率いるイメージです。霞が関の「課長」は、その上のレイヤー、民間企業で言うと部長程度のポジションですね。
経産省では、総合職で入省した人の多くは、20代後半から課長補佐、つまりマネージャーになります。その先、30代後半で「課長」になる人も、毎年複数名います。若いうちに大きな仕事が任される、実力次第で昇進も早い、というのは間違いありません。
なぜ今、経験者採用に注力するのか?

吉井 経産省ではかなり前から経験者採用に取り組まれています。
ただ本格的に人数が増え出したのはここ数年だと伺いましたが、なぜこのタイミングで経験者採用を本格化させているのでしょうか?
小林 経験者採用を始めたのは2003年からで、すでに22年間の実績があります。2025年4月には、経験者採用による入省者が150人を超えました。
その意味ではもともと本腰を入れていましたが、この5年はさらに踏み込んだ採用をしています。
理由の1つは、経験者採用のマーケットが成熟してきたことです。民間企業の転職市場はもっと早い段階から成長してきましたが、世の中全体の人材の流動化がぐっと進み、その中で公務に魅力を感じる人材の質もボリュームも大きく高まったと感じています。
もう一つの要因は役所側の話で、私たちとしても、多様性を重視し、様々な経験を積んだ方に来ていただくことの価値を一層強く意識したということです。
人材の流動化は霞が関も同じで、一度は霞が関で働いたけれども、別の挑戦をしてみたいと出ていく人が昔と比べて増えているのも事実です。
これは、必ずしもマイナスだけの話ではありません。霞が関を出ていろいろなところで活躍する人が増えれば、大きな根っこの部分で志を共有するアルムナイのネットワークが広がりますし、逆に「外から霞が関に来ていただき新たな仲間が増えることも良いことだ」とマインドチェンジが進む面もあります。
「新しい刺激や視点を持ち込んでほしい」

吉井 経験者採用で「外」から来る人材には、どのような期待を持っていますか?
小林 大きく言えば、新卒採用と同じです。なるべく早く組織に慣れて頂き、本当の意味で政策を担う一員になってもらうことが大切です。
あえて期待を言えば、経産省にたどり着くまでに新卒とは別の道を歩み、別の経験をされてきている方々なので、別の何か、新しい刺激や新しい視点を持ち込んで欲しいと思っています。
霞が関では重層的な意思決定がなされるため、仕事に丁寧さが求められることも多くあります。ただし、丁寧すぎることで、スピード感を欠くこともあるでしょう。
スタートアップなどで経験を積んだ方は、例えば「これ本当に意味ありますか」と疑問を持ち、屈託なく問題提起してくれる方も、実際に私の周りにもいました。そのような、慣習や現状に対する率直な批判精神は、大いに歓迎です。
また、経験者採用の方は、特定の業界や分野の専門的な知識をお持ちの方も多くいます。例えば電力システムや半導体技術について詳しい方などが、文字通り即戦力で活躍頂いているケースもあります。そうした専門性も大歓迎ですね。
吉井 その業界の専門知識がある方が、民間から来た場合、政策立案の現場でも過去の経験を発揮できるのでしょうか?
小林 もちろんです。ただし、特定分野の「専門知」は、いずれは古くなっていきます。
どこの分野で何を知っているのかということよりも、やはり本質的に重要なことは、どういう発想で、どういうものの見方ができ、どういう行動ができるのか、です。そういった思考力や実行力が高く、組織に付加価値を持ち込んでくれる人に期待しています。
吉井 なるほど。専門知識だけだったら、有識者にヒアリングすることもできますよね。
私が厚労省にいたときの経験なのですが、つながりがあった有識者の方などを委員会メンバーに推薦したとき、「今までアクセスがなかった方を連れて来てくれた」と感謝されたのですが、そういうことに価値を感じてくれるのかと驚いたのを覚えています。
小林 おっしゃるように、私たちは、いろいろな組織や有識者にアクセス可能ではあるものの、一つの組織で働いている以上、いわば「認識のメガネ」に囚われてしまう側面があると思います。私たちは常に、何らかの価値観や「常識」を前提にして、そうした「自分のメガネ」を通して世の中を捉えています。同じ組織に長らくいると、そのメガネがどうしても似通ってしまいますよね。
違うメガネで見たときには、こんな面白い人もいる、有益な意見もある、斬新な話もある、ということは、ものすごく価値のあることです。そうした付加価値を、同質性の外の人から持ち込んでもらうことが重要だと思います。
歯車の1つか、少数精鋭の1人か

吉井 民間企業から中央省庁に入りたい方の相談でよくあるのが、「自分がどれくらい物事を変える起点になれるのかイメージがわかない」「組織の歯車になってしまうのではないか」というものです。こうした不安についてはどう答えますか?
小林 実際に入ってみたら分かります、というのが乱暴な答えです(笑)。
国が抱えている政策は本当にたくさんあります。経産省だけでも見ても、◯◯政策と名前がつく政策の塊が、およそ10程度はあるでしょう。例えば、通商政策とか、エネルギー政策といった局単位のイメージです。それが、課や室の単位になると、省全体でだいたい200にも及びます。これは民間企業でいうと、社内に200ものプロジェクトチーム(ユニット)があるというイメージです。
そして、それぞれのユニットに何人くらいの職員がいるか想像してみてください。例えば、日米交渉を担う「米州課」。とても重要な課ですが、それでも課員は15人程です。
最近では、トランプ関税やUSスチールなどが話題で、重たい仕事が山ほどあることは説明不要かと思います。そうした仕事量を分子としたときに、分母はたった15人です。それを歯車だと感じるか、「アベンジャーズ」のような少数精鋭部隊の1人だと思うのかは、捉え方次第ですが、一人ひとりが一騎当千じゃないと、全くやっていけません。
経産省には、大きなプロジェクトが常に100も200もゴロゴロしていて、それぞれのプロジェクトは5人だったり10人だったりで担っています。逆に責任が重すぎるのではと心配になる人もいるかも知れません。
ただそこは、チームとしてみんなで支え合って進めていくので安心してほしいです。

吉井 「歯車になってしまう」という不安には、決められた範囲の仕事しかできず、裁量が持てないのではないか……という気持ちもあると感じます。
小林 その点も、実際に入ってもらったら分かります(笑)
時間的にも人的にも余裕があって、切迫していない状況では、細分化された仕事をみんなでゆっくり確認しながら進めるということもあるかもしれません。
ただし、現実は、のんびりとやっている余裕がない課題ばかりで、早い判断力と実行力が常に求められます。
「プロジェクトマネージャー」は課長や課長補佐ですが、プロジェクトを回し切るうえでは、マネージャーの指示待ちではダメで、全員が自走してもらわないと回っていきません。
細分化されタスクを受け身で待っていればよい、ということでは全くないのです。大きな課題に対して、何を今するべきか、どういう優先順位と順番ですべきか、誰と誰がやれるのか、逆に何はすべきじゃないのか……。それをチームの10人なら10人が、みんなで考えて、常に共有し続けないと仕事になりません。逆に、そうした活躍の機会は常にオープンです。
経産省では、経験者採用に関心がある方向けのリーフレット『国という舞台でしか見えない景色がある』も新しく作成しました。ぜひ読んでみてください。
皆さんの応募を楽しみに待っています。
▼リーフレットは下記よりご覧ください。
https://www.meti.go.jp/information/recruit/career/pdf/METI_leaflet_career_2025.pdf
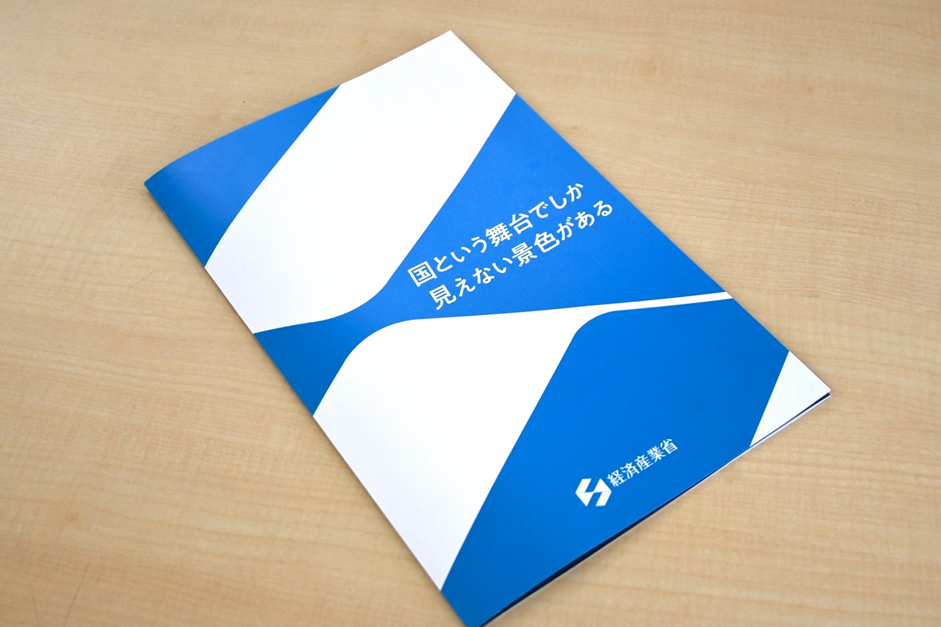
【申込〆切:10月28日正午】総勢15省庁登壇!霞が関キャリアフォーラムを開催します

2025年10月29日,11月5日,6日開催「霞が関キャリアフォーラム」のご案内
中央省庁への転職を検討中の方へ―――
「応募したいけれど、実態が分からない」「働き方やキャリア形成の違いを知りたい」
そんな声に応えるため、本フォーラムを企画しました。採用担当者や実際に中途採用で霞が関に入省した方々が登壇し、なぜ今、民間出身者が求められているのか、どのように活躍できるのかを具体的にお話しします。
▼登壇省庁
・10月29日(水)19:00-20:30
外務省・環境省・内閣府・農林水産省・防衛省
・11月5日(水) 19:00-20:30
金融庁・公正取引委員会・国土交通省・総務省・デジタル庁
・11月6日(水) 19:00-20:30
経済産業省・厚生労働省・こども家庭庁・人事院・文部科学省
▼詳細・お申込
https://lp.volve.co.jp/2025/10/forum/to
経済産業省への転職にご興味をお持ちの方へ!
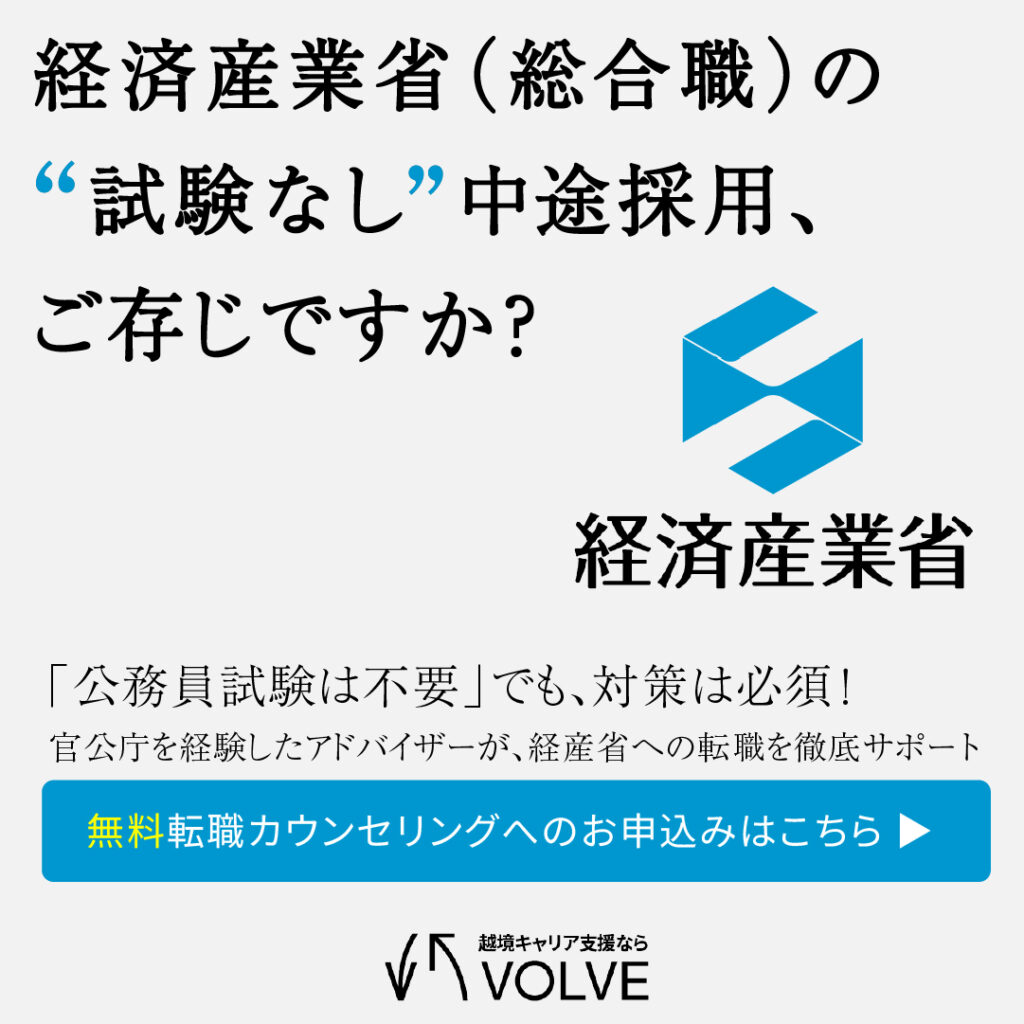
VOLVEは経済産業省からの委託を受け、総合職の経験者採用への転職支援を行っております。官公庁での勤務経験があるアドバイザーが専門的知見を持って転職活動を支援します。ご相談をお待ちしております!
▼詳細は下記からご覧ください!
https://lp.volve.co.jp/service/meti



