- 官と民をまたがる越境キャリア支援ならVOLVE
- 国家公務員、官僚から民間企業への転職
- VOLVE記事一覧
- 越境キャリア「舞台は世界」
越境キャリア「舞台は世界」 2025.03.12
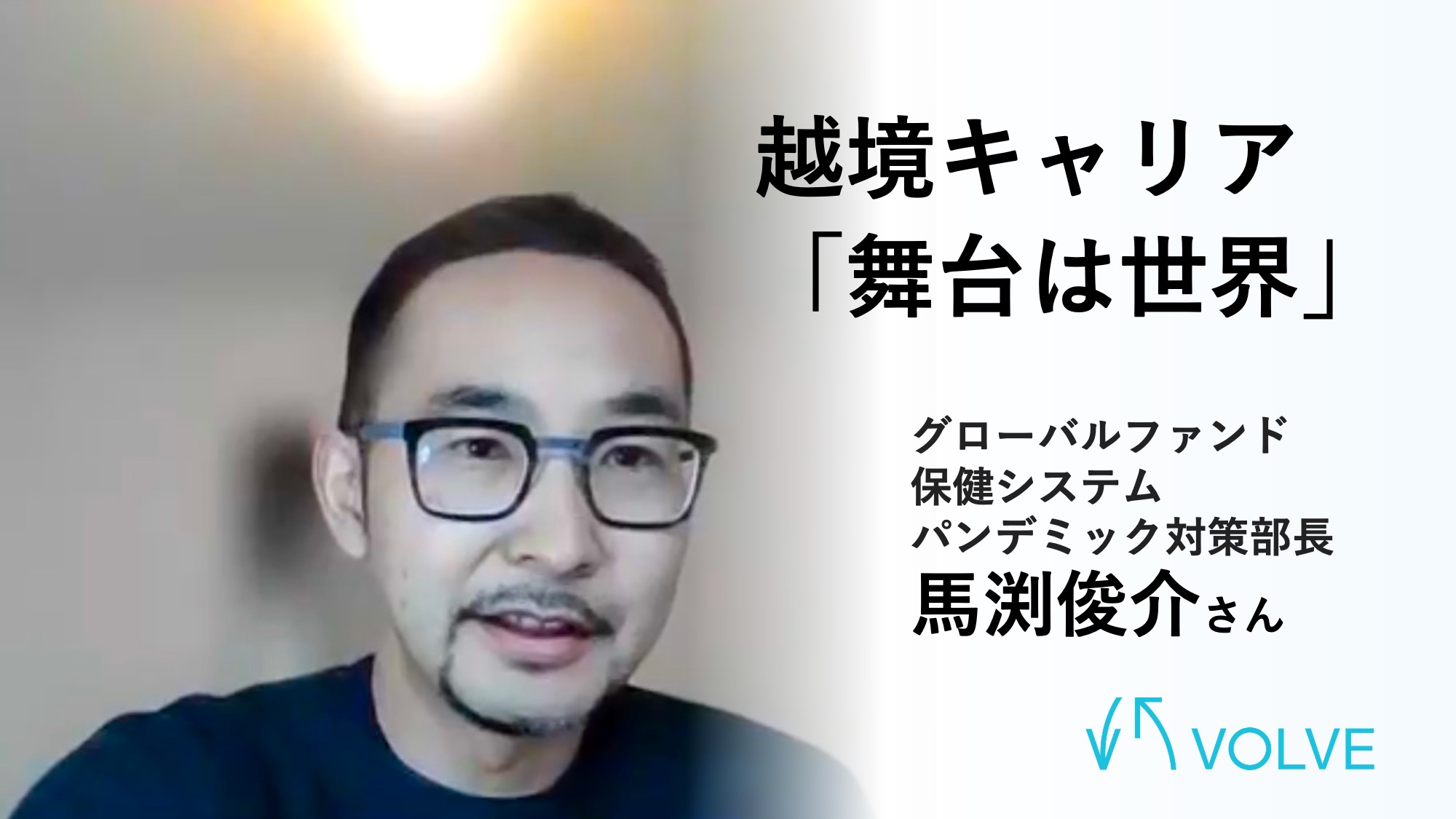
マッキンゼーやゲイツ財団、JICA、世界銀行と、民間企業や公的機関の垣根を超えたキャリアを歩みつつ、発展途上国などのグローバルヘルスの第一線で活躍し続けている日本人がいる。
現在は、アフリカやアジアにおける感染症対策(エイズ、結核、マラリアなど)を進める国際機関「グローバルファンド」で、保健システム・パンデミック対策部長を務める馬渕俊介さんだ。
世界を舞台に「越境キャリア」を実践し続けている馬渕さんに、これまでのキャリアの選択について聞いた。
<プロフィール>
馬渕俊介さん
2001年に東京大学を卒業し国際協力機構(JICA)に入構。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニー、世界銀行、ゲイツ財団を経て、2022年3月に国際機関・グローバルファンドで保健システム及びパンデミック対策部長に就任。2023年4月には母校・東大の入学式での祝辞も話題になった。
新卒でJICAへ「すぐ国際開発に携わりたい」
──発展途上国の支援に関心を持ったきっかけを教えてください。
学生時代にパプアニューギニアのカルリ族の儀礼を見たとき、その素晴らしさに感動したのをきっかけに、もともとは文化人類学者になろうと思っていました。「なぜ我々とは全く違う精神世界や社会、そして洗練された文化が生まれるのか。現代社会がそこから学べることは何なのか」を突き詰めたいと思い、学生時代には様々な国を訪れました。
様々な国を訪問した経験のなかで、遠隔地に住まうことで起きる医療アクセスの困難などを知り、「人々が文化や尊厳を大事にしながら生活を改善していけるサポートをしたい」「発展途上国の人々の可能性を広げるような仕事をしたい」と考えるようになり、大学卒業後はJICAへの就職を選びました。
JICAであれば新卒でもすぐに国際開発に携わることができ、また国際開発業界の中心の機関なので、その先のキャリアの見通しも立てやすい。というのも当時からすでに「国際社会で大きい仕事をしたい」と思っていて、「国連事務総長になりたい」とか(笑)、「世界銀行のような資金も国政へのアクセスもあるところで働いてみたい」というような思いがあったからです。
マッキンゼーで学んだ「民間流の課題解決」
──JICAの後、なぜマッキンゼーに転職されたのでしょうか?
JICAで4年半働いた後、ハーバードケネディスクールに留学をしました。パブリックセクターのベストプラクティスを学び、開発の現場に活かそうと思ったのですが、留学はむしろ民間企業に興味を持つきっかけになりました。
留学中には、民間出身の人たちが公共の世界にどんどん入り込んで行くのを目の当たりにし、民間企業の改革から学びながらパブリックセクターの改革が始まっているということを知りました。
私自身、経営コンサルティングの効率的な働き方を経験することで、民間企業の課題解決法や、人を巻き込み動かすスキルを身に着け、そのスキルをパブリックの世界に持ち帰りたいと思うようになりました。
──マッキンゼーの勤務を経て、グローバルヘルスの道に進みます。そのきっかけは?
ユニセフで働いている妻の赴任地が南アフリカに決まり、それに合わせて私もマッキンゼーの南アフリカオフィスで働く機会を得ました。その中で、グローバルヘルスの仕事に関わることができました。
現地の保健医療の問題というと、「効果的な薬が足りない」と言うようなイメージをすると思います。ですが実際にはもっと基本的なところで、先進国では簡単にアクセスできるものが、途上国の人たちには届かない状況がありました。
こうした背景には経済やインフラだけでなく、マネジメント、デリバリー、政治などの問題が複雑に絡んでいます。この業界の課題解決には、マッキンゼーで身につけたスキルが活きやすいと思いました。
南アフリカでの経験を経て、世界の保健医療の世界でこれからも仕事をしていこうと心を決めました。でもせっかくやるからには、ファンドレイズのような仕事ではなく、現場の保健医療プログラムの中核に携われる仕事をしたいと思いました。そのためには専門性をつけることが必要だと感じたので、今度はジョンズ・ホプキンス大学に入って、公衆衛生を学びました。
学業で公衆衛生の専門性を深めたことに加えて、民間企業でのオペレーション改善経験もあり、それを活かすビジョンも持っている──。その組み合わせが面白いと評価してもらえたことで、ついに世銀で働けることとなりました。
世界銀行での「エボラ出血熱」との戦い
──世界銀行で記憶に残っている仕事について教えてください。
世界銀行での1番大きな仕事は、エボラ出血熱の対策でした。
エボラ出血熱は感染が拡大していた西アフリカの国々にとって、国家存続の危機とも言える重大な局面でした。当時は大統領が「みんな死んでしまうんじゃないか」と心配するような危機だったのです。
私は娘が生まれたばかりで産休明けでしたが、世界銀行の上司からいきなり電話がかかってきて、「戻ってきたか? とんでもない仕事があるのだけれどやってくれないか」と打診されたのを覚えています。
また、ナイジェリア、タンザニア、そしてソマリアという紛争が残る地域で、保健医療の包括的なシステムを作ることになりました。
取り組んだのは「プライマリー・ヘルスケア」の仕組み作りです。プライマリー・ヘルスケアとは何かと言えば、例えば出産直後の母体や赤ちゃんが弱っている状態のとき、日本やアメリカでは医療上の支援体制があります。しかし多くの途上国では出産時の緊急事態や未熟児に対するサポートが機能していません。それゆえ母親や乳幼児が死んでしまうことも多く起きています。そのようなことなくすための基本的な保健医療サービスのことをプライマリー・ヘルスケアと呼んでいます。
例えばナイジェリアの僻地では、保健センターという場所自体はありましたが、全然機能していませんでした。
薬もない、スタッフはいるけどお客さんが来ない、いざ保健センターに来てもスタッフはちゃんと対応ができない、そもそも保健センター自体に電気が通っていない、出産のためのベッドなどの設備も整っていない……そんな状況でした。
その裏にある根本的な課題は、保健センターの人たちに権限がなく、各種支援で供給しているはずの資金も届かなかったために実際に利用できるキャッシュがなかったことです。
キャシュがないためにサービス改善も、薬へのアクセスもままならない環境でした。そこで私たちはまず、キャッシュが財務省から保健センターに直接届くような仕組みを作り、保健センターの人々が薬や設備、交通などの課題を、現地でプライオリティ(優先順位)をつけながら改善していけるような体制を作りました。同時にちゃんと結果が出ているのかモニタリングするシステムも作って、フロントラインにいる人たちがちゃんと働けるよう、バックアップする体制を整えました。
これはマッキンゼーにいたときに、大手スーパーの野菜売り場の利益改善をやったときのアプローチと同じでした。野菜売り場の準備と販売を担っていて、自分自身も家庭のお母さんとして「買い手」でもあるスタッフに売り場改善の権限を持ってもらい、それをサポートする。スタッフをサポートするマネージャーの能力が不可欠なので、スーパーでもやったマネージャー同士をペアにしてお互いから学び合うアプローチも展開したりしました。
ゲイツ財団が誇るスピート感と影響力
──大変貴重な経験ですね! 長く目指されていた世界銀行でしたが、その次のゲイツ財団を選ばれたのはなぜでしょうか。
世界銀行は国にフォーカスして働くことができますし、今でも特に思い出深い職場なので、いつか戻る可能性も十分にあると思っています。
でも「そのまま世界銀行にいたら“世界銀行の人“になるな」と思ったんです。
グローバルヘルスの世界でいえば世界銀行も、いち機関でしかありません。グローバルファンドやワクチンファンドのGavi、WHO、ユニセフなどさまざまなプレイヤーがいる中で、「グローバルヘルス全体のエコシステム自体を効率化するようなアプローチはないだろうか」と考えるようになりました。
世界銀行で私が担当したエボラ出血熱対策は記録的なスピードで行われたプロジェクトではありましたが、「もっとスピード感をもってできるはずだ」と課題を感じたこともありました。
ゲイツ財団に興味を持ったのは、ナイジェリアでゲイツ財団とポリオ(小児麻痺)撲滅の仕事をしたときでした。革新的で動きの早い仕事ぶりを見て、「こういうやり方は面白いな」と思いました。
ゲイツ財団はグローバルヘルスに関わる多様なプレイヤーに資金を提供していて、エコシステムを改善していく上ですごい影響力を持っていたのも魅力でした。あと純粋に、ビル・ゲイツと働けたら面白いだろうなという思いもありました(笑)。チームの運営を経験できるポジションでオファーを頂いたこともあり、世界銀行を離れることに決めました。
──ゲイツ財団ではどのようなお仕事をされたのでしょうか?
グローバルヘルスのあらゆる分野でものすごい影響力を持ち成果を上げてきたゲイツ財団ですが、私がこれまで働いてきた「保健システム」の分野では苦戦していました。ポリオのように一つの病気に絞って効果的なサービスの仕組みを作るのではなく、国のシステム全体を改善するのは至難の技だからです。
ゲイツ財団としては、方向性や集中すべき分野が定まらないまま仕事をしていたので、私はこれまでの経験をいかしつつ、新たな戦略を立案する仕事にチャレンジしました。
ゲイツ財団では、ビル・ゲイツに対して自分達のチームの戦略を話して納得してもらわないとチームが解体されたりして、実際のインパクトに結びつきません。その過程で戦略を詰め、それを効果的に伝えながら仕事を決めていくスキルが身についたと思っています。
ネイティブのアメリカ人でインスピレーションあふれるスピーチができる人であっても、ビルにプレゼンする時にはたくさん練習して、想定質問まで作って、その上で何度もデモを繰り返し、徹底的に準備していました。改めてコミュニケーションの重要さを気付かされた経験になりました。
ただ、ゲイツ財団での仕事はインパクトもあったのですが、次第に本当にやりたいことは財団のようにバックアップの立ち位置ではなく、実際に大きな資金を持ち、途上国に対してインパクトを出せるようなファイナンス機能を持つ組織で働くことだと気が付きました。
ちょうどその時期、グローバルファンドでこれまでやってきた分野を統括できるポジションが空いたこともあって、グローバルファンドで新しいチャレンジをすることを決めました。
グローバルファンドは結核、マラリア、エイズへの対策に関して、素晴らしいシステムを作って成果を上げていましたが、途上国でそこに特化したシステムだけを作っても、結局、国の保健医療システム全般を強化しないと、その効果は続きません。
グローバルファンドとしても、いつまでも支援を続けるわけにもいかないので、保健システムの強化を柱にして行く必要が認識され始めているタイミングでした。そこを立て直すチャレンジに取り組むために、グローバルファンドで仕事をすることに決めました。

グローバルファンドとして国際会議に出席したときの様子
グローバルファンドに参画「常に課題の中心にいたい」
──世界の公的機関で活躍している日本人はあまり多くはありません。世界で働くなかで日本人としての強みを感じることはありますか?
それぞれの分野やファンクションでチームはまとまっているが、異なるチーム同士が一緒に働かないといけないケースでは必ずしもうまくいかないことも起こります。
私の仕事はそれぞれの分野を横串で指すような保健システム全体の仕事なので、予防接種などトピックに特化したチームとの連携も不可欠です。それには日本でいう「調整力」や「根回し」が本当に大事になります。
例えば、それぞれのチームが独自の主張をしている状態では、「こう考えたら共通の目標が達成できるのでは」と考え・提案することでチームをまとめるスキルが求められると感じます。それは財団や国際機関、民間企業であっても同じだと思います。
あとは、相手が置かれている状況を理解した上で提案する力にも日本人は長けていると感じます。その分野のトップにいるような人たちだって同じ人間です。議論のロジックの裏には、感情的あるいは政治的なものもあり、自分が思うこと、自分が置かれている環境がベースになって行動が決まります。
「あの人はいま厳しいプレッシャーがあるから、こういう発言をしているんだな」など、そういう状況を理解して提案するスキルが本当に大切で、私の場合もその力をすごく重宝しています。

グローバルファンドで中央アフリカ共和国へ出張した際に撮影
──今後の展望を教えてください。
これからも目の前の課題にしっかり取り組みたいと思っています。
グローバルファンドで保健システムの分野に携わっていますが、グローバルヘルスを巡る状況が急速に変わりゆく中で、グローバルファンドが最も効果的な組織であり続けるためには、保健システム分野を軸にした改革が必要になります。非常に大きなチャレンジですので、この課題には何年かかけて向き合っていきたいと思っています。
それができた先については、まだイメージはないのですが、やっぱり常に課題の中心、直すべきところの中心にいたいと思っています。
それを直せるような人、例えばポジションとして組織で出世したいというより、グローバルヘルスでもっと大きなインパクトを出すとしたら、次の「大きなこと」は何なのか、その中心に身を置きたいと思っています。
越境キャリア支援ならVOLVE
VOLVE株式会社は民から官、官から民への越境転職を支援します。霞が関に特化した独自性の高い人材エージェントならではの求人案件、レジュメ・面接対策をご希望の方はぜひ、弊社ホームページからお問い合わせください。個人起点の越境キャリア・ジャーニーを伴走支援します。
国家公務員への転職にご興味をお持ちの方へ おすすめ情報
現在募集されている求人情報をまとめて把握!
さらに解釈が難しい「霞ヶ関用語」を一般的な言葉に置き換えて検索できる機能も付いています。
▶︎国家公務員の求人情報 ヒント付き検索
国家公務員の給与水準はご存じですか?こちらのシミュレーターで簡単に目安給与を把握することができます。
▶︎年収シミュレーター
中央省庁への転職カウンセリングサービスも提供中です。履歴書や職務経歴書、小論文の作成から面接準備まで、あなたの個性と経験を引き出すサポートを行います。
▶︎中央省庁への転職カウンセリングサービス
幅広いキャリア選択を知りたい中央省庁勤務の方へ
国家公務員での経験は民間企業での仕事には活かせないと思っていませんか?公務員の代表的なスキルである「調整力」を、幅広い企業で活かせる「ポータブルスキル」として解説しました。
▶︎解剖!霞が関 「調整力」はビジネスでも使える?
「いつかこの仕事にやりがいを感じるのか?」「成長できているのか?」「市場価値はあるのか?」そんなモヤモヤを感じている方へ、ぜひ無料キャリア相談をご活用ください。
▶︎キャリア相談のお申込はこちら
【申込〆切:10月28日正午】総勢15省庁登壇!霞が関キャリアフォーラムを開催します

2025年10月29日,11月5日,6日開催「霞が関キャリアフォーラム」のご案内
中央省庁への転職を検討中の方へ―――
「応募したいけれど、実態が分からない」「働き方やキャリア形成の違いを知りたい」
そんな声に応えるため、本フォーラムを企画しました。採用担当者や実際に中途採用で霞が関に入省した方々が登壇し、なぜ今、民間出身者が求められているのか、どのように活躍できるのかを具体的にお話しします。
▼登壇省庁
・10月29日(水)19:00-20:30
外務省・環境省・内閣府・農林水産省・防衛省
・11月5日(水) 19:00-20:30
金融庁・公正取引委員会・国土交通省・総務省・デジタル庁
・11月6日(水) 19:00-20:30
経済産業省・厚生労働省・こども家庭庁・人事院・文部科学省

